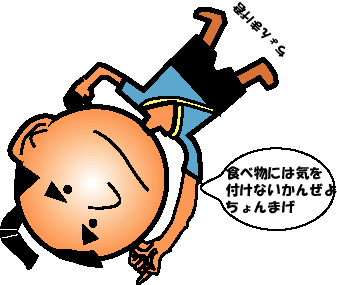
下の表は一般的にいわれているもので、食事は人によって良い悪いがあるので
自分に合ったものを見つけましょう。
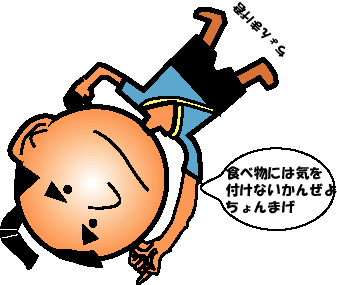
| 穀類 | もち | ・でんぷんがアルファ化されて消化しやすい 形になっているので良い。 |
|---|---|---|
| パン | ・食パン、柔らかめのフランスパン、バターロール、蒸しパンなどは良い。 ・クロワッサン、デニッシュなど生地全体に脂肪を多く含むもの、また油で揚げた菓子 パン、レーズンの入ったもの、ライ麦パンは避けた方が良い。 ・調理パンなどを買う場合は調整時間の新しいものを選び、中身もできるだけ脂肪の 少ないものにする。 | |
| 麺類 | ・麺類は十分に噛まないで、簡単に飲み込む場合が多いので唾液中の アミラーゼの作用を受けにくい。→良く噛んで食べる。 ・うどん、ひやむぎ、そうめん、スパゲッティ−、ビーフン→柔らかく煮る。 ・そば、ラーメン、インスタントラーメンは避けた方が良い。 | |
| 米類 | ・米飯、粥は良い。 ・玄米は、精白米に比べビタミン類などの栄養成分量が多いが、消化吸収が悪いので 避けた方が良い。→胚芽米にするか、あるいは精白米にビタミン強化米や小麦胚の 油のカプセルなどを混ぜて炊くと良い。 | |
| とうもろこし | ・とうもろこし、ポップコーン、コーンフレークなどは難溶性で繊維も固いので避けた方が 良い。 ・コーンスターチ(でんぷん)は良い。 | |
| いも | こんにゃく | ・こんにゃくの主成分であるグルコマンナンは、水溶性だが消化されにくいので避けた 方が良い。 |
| 他の芋類 | ・イモ類(じゃが芋、里芋、長芋など)は繊維が多く、発酵しやすいので、一度に食べる量 は少量にして、つぶしたり、裏ごししたり(特にすじの多いさつま芋)調理に工夫する。 | |
| 砂糖類 | 砂糖 | ・上白糖など精製された糖分の摂取は控えたほうが良い。 |
| はちみつ | ・ボツリヌス菌が入っているので注意。 | |
| オリゴ糖 | ・使用量によっては、お腹がゆるくなるので量の加減が必要。 | |
| 菓子類 | 和菓子類 | ・豆類の皮の部分が残りやすいので、つぶあんよりも、こしあんにする。 ・豆菓子は避けた方が良い。 ・せんべいは豆ごまが入っていないもの、また油で揚げたり、まわりに唐辛子の ついていないものが良い。 |
| 洋菓子類 | ・パイやドーナッツ、生クリームやチョコレートでデコレーションされているケーキ類は 脂肪が多いので避けた方が良い。 ・ゼリー類は良いが、ババロア、ムースには生クリームが使用されているので注意が 必要である。 ・ビスケット類は脂肪が多いので、たくさん食べないようにする。(幼児向けのものは 脂肪の含有量が低い) ・クラッカー類も脂肪の低いものを選び、油で揚げたクラッカー、スナック類は食べない。 ・チョコレートは脂肪が多く、またシュウ酸も多く含んでいるので避けた方が良い。 | |
| その他 | ・チューインガム、あめは良い。 | |
| 油脂類 | 油脂類 | ・脂肪の使用量を減らす。 ・動物性の脂肪、リノール酸系の油脂(nー6系)を減らしてα−リノレン酸系の油脂(n-3 系)か吸収の良いマクトンオイルを使用するようにする。 |
| 種実類 | 種実類 | ・ピーナッツやアーモンド、ゴマなどの種実類はn-6系の脂肪が多く、また繊維も固い ので避けた方が良い。 |
| 豆類 | 豆類 | ・豆類は消化されにくく、皮の部分が残りやすいので、食べる量を少なくする。小豆、 うずら豆などの煮豆は裏ごしする。 |
| 豆腐類 | ・豆腐は木綿、絹ともに良い。油揚げ、厚揚げなど油で揚げたものは湯通しして油抜き してから使用する。 ・おからは豆腐を作る際の大豆のかす(皮)なので、食べない。 | |
| 豆乳 | ・豆乳は良い。 | |
| 味噌類 | ・こした味噌の方が良い。つぶや麺が気になるようなら味噌こしでこす。 | |
| 納豆類 | ・なるべく避けた方が良い。使用する際は量を減らす。 ・ひき割り納豆は大豆を煎って割砕し、脱皮したものを原料としているので、 危険性が少ない。 | |
| 緑豆春雨 | ・緑豆のでんぷんから作られた春雨で繊維が少ない。でんぷん春雨より煮崩れしにくい ので、白滝の代用に鍋物や酢の物に代用できる。 | |
| もやし類 | ・繊維が長いので、そのままの場合は避け、使用する際は、根を取り小さくきると良い。 | |
| 魚介類 | 魚類 | ・魚類は何でも良い。できるだけ旬のものを食べるようにする。背の青い魚は炎症を 抑える作用を有しているため、積極的に摂取するように努める。 ・小魚もカルシウム源として良い。 ・缶詰は油付けのものは避け、水煮にする。 ・魚卵類は鶏卵と栄養成分が似ているが、DHAも多く含んでいる。食べ過ぎないように ・はんぺん、蒲鉾などの練り製品は良い。 |
| 甲殻類 | ・いか、海老、たこなどの甲殻類は消化が悪いので食べる量は少量にする。 ・するめいか、小えび、くらげなどは繊維組織が固く消化効率が悪いので口の中で噛ん だり、しゃぶるだけにとどめる。 | |
| 貝類 | ・貝類は消化が悪いので控える。あさり汁やしじみ汁などにするとタンパク成分が溶け るので汁だけで飲むのも良い。 ・牡蛎は良い。 | |
| 獣鳥肉類 | 肉類 | ・肉類は「食事性抗原」として炎症を更新させるので使用するときは脂肪の少ない柔ら かい部分が良い(もも、ひれなど)。 ・ハム、ソーセージなどの加工品はできるだけ脂肪の少ないものを選ぶ。 湯通しすると着色料、保存料などが少しは抜けると言われている。・レバーは鉄分を 多く含む優れた食品であるが、解毒器官でもあるので、流水でよく洗ってから使用する。 ・調理する際には脂肪をできるだけ使わないようにする。 |
| 卵類 | 卵類 | ・タンパク源に富み、消化吸収も良いが、脂肪(n-6系)を多く含む。 ・1日に1から2個。 |
| 乳類 | 牛乳類 | ・牛乳は(n-6系)が多いので、低脂肪(ローファット)牛乳もしくはスキムミルクにする。 ・乳頭不耐症がある人は乳頭が分解されたアカディ牛乳にする。 |
| ヨーグルト類 | ・腸内細菌を整える働きがある乳酸菌を含むヨーグルト類は積極的に取る(オリゴ糖と ともに摂ると効果的)。 | |
| アイスクリーム | ・できるだけ乳脂肪の少ないものにする。 | |
| チーズ類 | ・脂肪を多く含むので、使用料は少量とする。 | |
| 野菜類 | 野菜類 | ・ごぼう、はす、筍、蕗、ぜんまいなど繊維の固いものは避ける。 ・葉さいるい(小松菜、キャベツなど)は柔らかくゆでて、茎は避け、葉の部分を小さく 切って食べる。 ・茄子、胡瓜、トマトの皮は消化されずに閉塞の原因となりやすいので皮をむく (種も消化されにくいのでトマトは種も取る)。 ・南瓜も皮をむき、繊維が気になる時は裏ごしする。 ・根菜類(大根、人参、蕪など)は比較的繊維が柔らかいので使用してよい。 ・花野菜類(ブロッコリー、カリフラワーなど)は柔らかく茹でて、茎は避け花の部分を 少量用いる。 ・葱、玉葱、うど、セロリなどは繊維が長いので繊維に直角に包丁を当て繊維を切って から少量使用する。 ・野菜類の繊維は量自体を減らす、煮て柔らかくする、小さく切る。 ジューサー、ミキサーなどで細かくする、裏ごしして除くなどが基本である。 ・野菜不足のビタミン摂取は、野菜ジュースで補う。 |
| 果実類 | 果実類 | ・ペクチンの多い果物を摂取するように努める(バナナ、りんご、桃など)。 ・果物の皮や種、柑橘類の袋は消化されないので、皮、種、袋は残すようにする。 ・柑橘類の酸味が強いものは腸に刺激を与えることがあるので注意する。 |
| きのこ類 | きのこ類 | ・きのこ類の繊維は人間の消化酵素では分解されないので、出し汁を利用する。 またはみじん切りで少量使用する。 |
| 藻類 | 藻類 | ・のり、わかめなどはよく煮て少量使用。 ・こんぶ、ひじきなどは避けた方が良い。 |
| 嗜好飲料類 | 嗜好飲料類 | ・アルコール、炭酸飲料、カフェインなどは腸を刺激して下痢を助長するので控えたほう が良い。 |
| 調味料類 | 調味料 | ・醤油、ソース、コンソメ、ケチャップ類は良い。 ・酢は腸を刺激するので使い過ぎないようにする。 ・ドレッシング、マヨネーズは脂肪が多いので、少量にするか低脂肪のもの、ノンオイル のものに変える。 ・香辛料は腸管を刺激して下痢を助長するので控える。カレー粉、 唐辛子は特に注意。 |